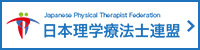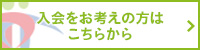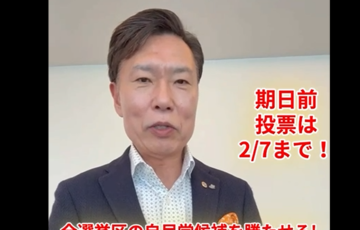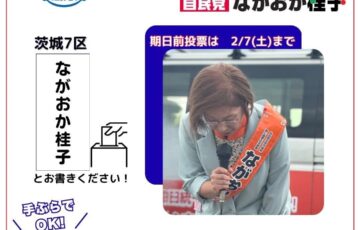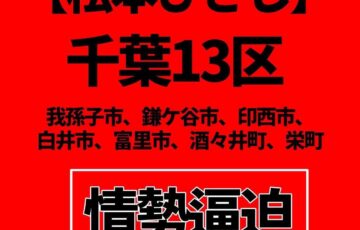2025年6月26日(木)に厚生労働省中央社会保険医療協議会で分科会が開催され、その中でリハビリテーションに係る現状と課題について議論がなされました。
まず、リハビリテーションの総論では、入院中は患者の病期に応じて、身体機能の回復、生活機能の回復、廃用予防とそれぞれの目的に沿ったリハビリテーションを適切に提供する必要があると示されました。
生活機能回復リハビリテーションについては、在宅復帰を考える上で、身体機能や活動の回復、自助具等の使用によりADLを獲得し生活機能の回復を目指すことや、退院後の自立を支援する視点が重要となります。現在、生活機能回復の加算で排尿自立支援加算という項目がありますが、その届出数は少なく、増加も緩やかとなっています。また生活の場に近い環境でリハビリテーションを実施できる医療機関外でのリハビリテーションは1日3単位に制限されています。しかし、3単位を超えて実施を行った例も一定数みられています。
退院支援においては、退院前訪問指導が再入院の頻度低下、退院後ADLの向上等の効果があると示されています。しかし、算定回数は少なく実施率は低い状態です。実施している場合は、理学療法士、作業療法士をはじめ多くの職種が関わっています。回復期リハビリテーション病棟等に入院する高次脳機能障害の患者について、退院前の情報提供の不足、医療機関と障害福祉関係機関とのネットワークの問題等から、退院後に適切なサービスに繋がることが困難であるとの調査結果がありました。
疾患別リハビリテーションの早期介入について、ADL回復、廃用予防から早期リハビリテーションの介入が重要であると報告されています。2024年に新設された急性期リハビリテーション加算では、入院からリハビリ開始までの要件が設定されておらず、3日目以降に疾患別リハビリテーションを開始する例が約4割と報告されています。
上記の現状をどのように評価するのか、また現状を踏まえて、更に検討を進めるべき事項についてどのように考えるかが、今後の課題として示されました。
出典元 厚生労働省HP 令和7年度第5回入院・外来医療等の調査・評価分科会
P129~156